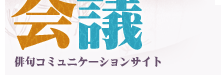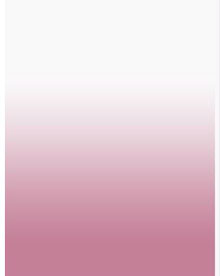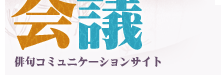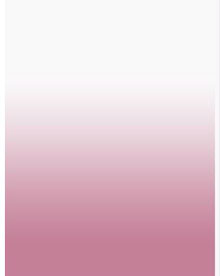|
| 論文を読む会議事録 |
不易流行は近代の原点
―岩岡中正氏の発言を要約する― |
谷地快一 |
〈「近代」とは人間による作為、つまり一切を自分の小さな自我で作っていくやりかた〉を学んだ時代である。「現代」とはその〈近代の行き詰まり〉の時代で、「老いてきた近代」といえる。つまり〈一切が自己中心的になり、物事を見るのにすべてが分析的になり散文的になり、詩が失われてしまった時代〉で、〈人と人、人間と自然との関係、挙句の果てには自我と身体との関係までも崩壊してしまい、バラバラになった世界〉である。〈真の知性が枯渇し、貧困になった時代〉といってもよい。俳句に関して言えば、〈非常に実感から遠ざかった言語遊戲〉になってしまった。
もとより詩は「真の知性」である。つまり、詩には内発力・生成力があり、〈一切を総合する力〉が備わっている。それは〈相異なるものから、それを超えた全く異質な高次元のものを作り出す〉想像力(imagination)によって生まれるのであり、〈言葉を適当に組み合わせて新奇なものをつくりあげる〉空想(fancy)の産物ではない。
ではこの「老いてきた近代」をいかにして超えるか。それは「近代」の原点に帰ることである。もともと「近代」がめざしていた「生きた自我」、つまり芭蕉のような「開かれた自我」を完成させるために、もういちどモダンの原点に帰ることである。創造のエネルギー(流行)と伝統(不易)との相互の往復運動を通して、〈生き生きとした感動をもって、新しい見方や価値観の中に身を置いて、★自己生産論(オートポイエティック)に生きていくという〉ところから新しい伝統が創出されるであろう。
〔谷地注〕★「自己生産論」は「自己生産的」の誤植か。とすれば、その意味するところは、向上心を持って主体的に生きて、その結果として生まれてくる感動を形象化する、という脈絡になるであろう。
|
|
|
 |
|
 |