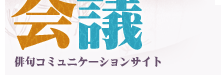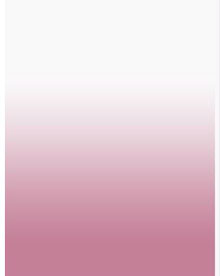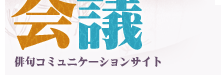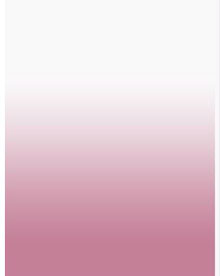■200905_02
海紅 2009/05/15-13:46 No.[6364]----------------------------------------
リラ冷えや僧となりゆく友一人
佐和子 2009/05/16-21:07 No.[6373]----------------------------------------
清楚で厳粛の雰囲気ですね。
ここは出立する友を見送る姿が目に浮かびます。
自ずから合掌、そして友は振り返りは絶対ないところと思います。ああ、私には言葉がなく悲しいです。
何故か泣けます。困ります、美しさに圧倒されます。
佐和子 2009/05/18-22:26 No.[6387]----------------------------------------
私のあまりも直情的な悲しいとか泣くとかの投稿文には小首を傾げたお方もおありでしょう。表現が幼稚であリ恥ずかしく思います。
僧となり行く友の決心と遂行それに作者と夜を徹しての語らいもおありでしょう。お二人の姿も描き語らなければと焦ります。そして友の変わらぬ決意に尊い像を目の前にする幻想、ここはもはや、別の世界の人と吾に帰らず放心状態のままといたします。
佐和子 2009/05/19-06:11 No.[6390]----------------------------------------
吾のみの為に生きるのでない友には厳しい修行が待っています。まだ朝夕は寒く耐えられるだろうかの心配。
しかし「苦しく限界を感じたらボクの家の扉を何時でも叩いてくれ」とは今は言えません。
――ずっと前の話だったでしょうか。
毎年リラの花咲く頃に思いだされる凄く立派なヤツから元気にしていると便りが届いたかも知れません。
佐和子 2009/05/19-22:42 No.[6394]----------------------------------------
こんばんわ。また此処に来ましたことをお許し下さい。
先ほど、札幌で生活している気のいい友人のGと電話しました。久し振りの「何よ、急に」からは略します。
佐 「リラ冷えについて教えて欲しいの」
G 「一口には言えないわ。零下20度の冬を少なくと も10年は越した経験がないと無理ね。それもね
若いうちでないとこの季節はだめよ」
この続きは明日のこの時間ごろにさせて下さい。
小出富子 2009/05/19-22:58 No.[6395]----------------------------------------
リラの花を見ようと「ねむの木の庭」に行ってみたのですが、あいにく咲き終わっていました。管理の方に伺いましたら、四月下旬から五月上旬に咲くそうで残念でした。リラはフランス語と説明されていましたので、「僧となりゆく友」は、素敵な人とイメージしています。
佐和子 2009/05/20-21:09 No.[6400]----------------------------------------
昨日の続きです。恐れ入ります。
G「リラ冷えと僧になりゆくは一対なの。これは此処 に長く住んだ者でなくては分らないわ。それはね
この句には香りがあるの。あなたには無理ね」
著名の作家の紀行文でもその土地に長く住んだ者には
仕方がないところがあるように。いやはや、きのう今日と勿体をつけたようですみませんでした。
佐和子 2009/05/21-21:39 No.[6407]----------------------------------------
尼寺に行くつもりはとかは過去にも現在もございませんが、あの世には何時かはご厄介になるのだなあと考えることは時にしてあることは正直あります。
こうして生きていられるのは多くの人に支えられているのだと今日この頃は心底より思うようになりました。
いろいろの拙い投稿を許して下さいまして感謝します。
では今回はこれにて失礼します。
天野 さら 2009/05/21-23:22 No.[6408]----------------------------------------
この句の「僧となりゆく」は「なって出かけて行く」では無く、「なりゆく」で今までと違って、例えばなんとなく僧侶のようなひきしまった顔つきであったり、動じない落着いた態度や、顔つきであったり、心構えができたのか話し方も静かで、澄んだ心が感じられるようになったとか、様々な変化を感じ取って詠んだのではないでしょうか。もうこれまでのように気楽に会ったり飲んだりはできなくなるだろう、と寂しく思っているように感じられます。友達が友達でなくなっていくような寂寥感と世を棄てるという美しくも潔い友の心境、「リラ冷え」の季語が非常に効果的です。リラは北海道、とすぐ思い浮かべるほど強い結びつきがあるようです。関東ではなかなかリラ冷えの句が作りにくいのではないでしょうか。佐和子さんのコメントにありましたが生粋の北海道人の〈リラ冷え」の句が有りますので引きます。旭川に生まれ住んだ、今は亡き叔母は卒壽の記念に句集を出しました。その中の三首「リラ冷えの残る朝の庭いぢり」「「リラ冷えや今日は一日をもの言はで」「リラ冷えや遭はずもがなの人に遭ひ」これらの句は何歳ころの作かは分かりません。子供の頃からかわいがってもらっていたおばの俳句を紹介できて何よりうれしいです。
「リラ冷えや僧となりゆく友一人」の句に感謝致します。
つゆ草 2009/05/22-09:38 No.[6410]----------------------------------------
さらさんお久しぶりです。叔母さまの句しっとり感ありとても素敵ですね。リラの花は歌にあったような気がして今一ピンと来なかったのですが、ライラックの花と分かり私の大好きな薄紫と白があり、札幌の花ということも分かりました。花言葉は「初恋の感動」「若き日の思い出」らしいです。きっと若き北海道時代の先生の思い出の一ページなのでしょう。「リラ冷え」の季語が非日常的な「僧となりゆく」に感応して確かに寂寥感とともに静謐感も漂う清らかな感を受けました。
天野 さら 2009/05/23-09:37 No.[6418]----------------------------------------
三木さん本当にお久しぶりです。忙しさを口実に芭蕉会議を怠けていまして申し訳なく思っています。今回の先生の句で「リラ冷え」の入った叔母の俳句がすぐに思い浮かびました。北海道という共通点がリラの花についての思いは通じるのではないかと・・。三木さんの暖かいコメント、嬉しく思います。花言葉もまた素敵です。初めて知りました。リラという音も澄んだ響きで心惹かれます。紫や白の色、花も小さいのでどちらかというと地味な感じですが秘めたものを感じますね。「若き日の思い出」の花言葉、三木さんが指摘されたように先生の若き日の思い出、それも忘れられないほどの深い思い出のようで、胸がキューんと締め付けられるような感慨になります。そうだ、あの時は丁度リラの花が咲いていた、途切れ途切れの会話だったなどと、勝手に想像してしまいます。リラの花と僧と友情、そんな事柄が薫り高い俳句にしているのではないでしょうか。この句でリラの花が、今まで以上に好きになり、深い思いを投じてみることになります。将に俳句の力、言葉の力、心の力です。
照香 2009/05/30-12:49 No.[6434]----------------------------------------
はじめまして。この句の凛とした美しさに魅せられて思わず投稿したくなりました。この僧になられた、ご友人は女性かしら?だとすると、とても親近感が湧きます。5年ほど前出家しようと決意し、周りの方々に今生の別れを告げたときのぴんと背筋を伸ばしたような清々しい気持ち。「リラ冷え」はみなさまのコメントから本当に厳しい寒さと推量していますが、出家する自分への厳しさがよく表れていると思いました。「リラ冷え」がことのほか美しく輝いていますね。そしてもう一点。「友一人」というところも気が引き締まる思いがします。家族、友人とも別れ、地の神様にもお礼を言って、あちらの世界へ旅立つ時、われわれは徹底的に一人です。ひとりで未知の門をくぐるのです。そこに甘えは許されないのです。この句に美しくも厳しい仏の世界が描かれているように思いました。
|
|