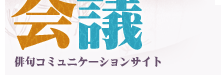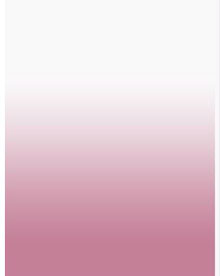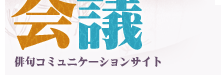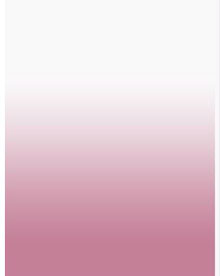■200905_01
海紅 2009/05/01-13:54 No.[6303]----------------------------------------
水面から文字摺草に風移る
佐和子 2009/05/02-21:34 No.[6310]----------------------------------------
小学校の遠足に見た記憶がありましたが何分まあ……として植物図鑑をしげしげと眺めました。
螺旋状に咲く花は左巻きと右巻きがある特異さはこの句に行き会えないと知らないままのこと。
湖水か沼かの近くで坐っているか横になっているか、程よい風がきているのは、どちらにもでしょう。
ポプラ 2009/05/03-21:18 No.[6312]----------------------------------------
文字摺草という名を忘れていました。ネジバナといいならわしていましたので。もうその季節なんですね。
意外に逞しい花で、中央分離帯の芝生の中によく見かけます。以前、鉢植えにして大事にしていましたら、翌年は芽を出しませんでした。句からは涼やかな風を感じます。
佐和子 2009/05/05-22:10 No.[6320]----------------------------------------
私、連休中だというのに今年も何処にも出かけるのでもなく小さな棲みかで息を潜めいています。あと一日。
ところでこの句は風の音はどうなんでしょうか。私には
聞えてきません。勉強が足らないから鈍なのですね。
ーん。ですが小鳥の声など勝手に想像はしています。
浅草っ子 2009/05/06-10:51 No.[6324]----------------------------------------
この風の音は聞こえないって、繊細な鑑賞だと思います。小鳥の声を聞いてしまうのもすてきです。俳句の味わい方を教えていただいたって感じです。
佐和子 2009/05/08-21:14 No.[6334]----------------------------------------
今日のですね帰宅途中の夕立の凄いこと(南関東)
私の住まいの場所ぐらいは、告知こんな位置ですよ。
これからは草花が生き生きとし木立に緑が増して黒々となります。明日は気温も日焼けも気になります。
立ち話日傘ひろげてより弾む 海紅
佐和子 2009/05/10-22:14 No.[6340]----------------------------------------
風移るは言葉自体も少し停止してまた動きました。
風に対して、ときめきを感じそして、たかぶりを。
それから間もなく、やすらぎを感じます。
今日も時季としては暑かったですが風がありました。
むらさき 2012/06/23-20:15 No.[7898]----------------------------------------
流れのうつくしい作品です。
もともとは、ネジのように捩れた形状から「ねじ花」・「捩摺(もじずり)」といわれていたようですが。それが「文字摺草」という言葉に変身し、季語として定着したのは、何故でしょう。何時ごろからなのでしょうか?
たしかに、穂の連なる形状は 単純な象形文字のようにも見えますが。 螺旋状のものもあるそうで、それなら水面に映っているときは 複雑な文字の形にも見えるかも知れないな〜と思ったり。
もし、「ねじ花」・「捩子花」・「捩摺(もじずり)」という表現であったら、この句は単なる写生句にしか見えなかったかも知れない。「文字摺草」という表現が、この句に華やぎをあたえている。「文字摺草」が、とても生きた句だと思う。
作者は、水面をわたっていた風が「文字摺草」に移る ”その瞬間・その一瞬の、風・風の気配 ”を、お詠みになりたかったのではなかろうか? 句の主語も、「風」。
しかし、風そのものを 感じることはできるが、見ることはできない。風が移ったことを知らせてくれるのは、文字摺草。 つまり、その時「文字摺草」は、一瞬の風を見せる・引きたてるための”舞台装置”の役割をはたすことになる。
淡紅色の小花をつけた ねじ状の草が水面に映る姿は、どんななのだろう? それが風にそよぐと、どんなふうに変わるのだろう? 平仮名の形をした花文字にみえるのだろうか? 風がそよぎ、そこへ光が屈折したら 水面に映る「文字摺草」はどんな輝きをみせるのだろう?どんな陰影をみせてくれるのだろう?
そして、それらにあらわれる”変化”こそ、風が、みえないはずの風が、たしかに そこに存在し 過ぎていったことの証しとなるのである。
詠み手が「時」を意識するとき、句には四次元の世界・時空間があらわれてくる。しかし、考えてみれば、私たちは 通常 その時空間に生活しているわけで、そのこと自体にさほど意味があるわけではない。作者が 切りとりたいのは、一瞬。 そこに、詩を感じ 詩をみたからである。その一瞬をおのれの中に定着させたい、作品として昇華したいという一心からなのであろう。
この句は”その束の間の時”を表現しょうと、詠まれたのではなかろうか?
みやびな王朝文化の香りをも感じさせ、うつくしい作品です。
夏霧やうすむらさきに野そめゆく むらさき
|