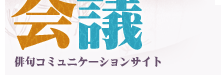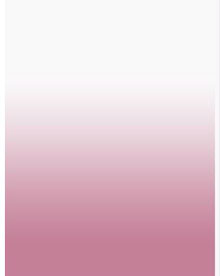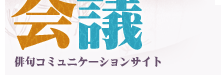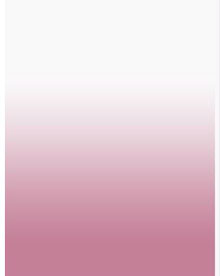| 【西行忌】旧暦二月十六日。弘川寺(大阪)、鴫立庵(神奈川県大磯)などで今も忌を修す。 |
| ◎夫のため旅支度して西行忌 |
大江 月子 |
日常に材を得て秀句。 |
| ◎花あればどこもまほろば西行忌 |
安居 正浩 |
源義句を踏むにしても佳句。 |
| ○西行忌〈海紅ブログ〉に花片舞ふ |
水野千寿子 |
こんな句があってよい。 |
| ○会へなくて死にたいやうな西行忌 |
西野 由美 |
こんな句があってよい。 |
| ○西行忌われの生れし月なりき |
尾崎喜美子 |
こんな句があってよい。 |
| ○誘ひあひ古書店めぐる西行忌 |
櫻木 とみ |
ありそうな景である。 |
| ○西行忌大枝活けたる無名庵 |
谷地元瑛子 |
「大枝」漠然とするが。 |
| ゆく水の堤にしばし西行忌 |
松村 實 |
「ゆく水」抽象的。 |
| 山越えてちりぢりに雲西行忌 |
梅田ひろし |
「雲ちりぢりに」 |
| 西行忌花も嘆いておくれ馳せ |
中村美智子 |
描写不足なり。 |
| 西行忌卒論テーマは歌人たり |
清水さち子 |
「歌人たり」利かず。 |
| 行きずりにゆかりの寺か西行忌 |
柴田 憲 |
「行きずりに」利かず。 |
| 西行忌来れば父の忌父の声 |
根本 文子 |
「父の声」利かず。 |
| 一千の花びらの影西行忌 |
小出 富子 |
「一千の」利かず。 |
| 取り寄せし歌集うるはし西行忌 |
つゆ草 |
「うるはし」利かず。 |
| 武士を捨て桜を愛でし西行忌 |
天野喜代子 |
題をもてあます。 |
| 虚空より鳥の声降る西行忌 |
堀口 希望 |
題をもてあます。 |
| 一人居の山辺の友訪ふ西行忌 |
天野 さら |
題をもてあます。 |
| 天麩羅のなほほろ苦し西行忌 |
ひぐらし |
題をもてあます。 |
| 西行忌いつもの店にまた居ます |
千年 |
題をもてあます。 |
| 西行忌鈴鹿の峰の青遥か |
堀 眞智子 |
題をもてあます。 |
| 荒磯やたはらおむすび西行忌 |
谷 美雪 |
題をもてあます。 |
| 覚めて花眠りて花を西行忌 |
吉田いろは |
題をもてあます。 |
| 南天にかかる眉月西行忌 |
ちちろ |
題をもてあます。 |
| 山家集鞄に入れて西行忌 |
鷲田 裕克 |
題をもてあます。 |
| 西行忌 氷川の杜に 能舞台 |
米田かずみ |
題をもてあます。 |
| 千の風花の風吹く西行忌 |
五十嵐信代 |
題をもてあます。 |
| 歌枕胸にめぐりし西行忌 |
尾崎 弘三 |
題をもてあます。 |
| 夜は夜の顔持つ寺よ西行忌 |
礒部 和子 |
題をもてあます。 |
| 老僧の洒脱な法話西行忌 |
金井 巧 |
題をもてあます。 |
| 光陰を旅する心西行忌 |
大原 芳村 |
題をもてあます。 |
|
| 【山笑ふ】芽吹き始めた山容をいう。 |
| ◎口おほきく開けて磐梯山笑ふ |
堀口 希望 |
「磐梯山」で写実を果たした。 |
| ◎送電線大きくたるみ山笑ふ |
梅田ひろし |
景情整う。 |
| ◎野うさぎの糞新しく山笑ふ |
西野 由美 |
景情整う。 |
| ◎夢の中で夢もらひけり山笑ふ |
天野 さら |
哀れもおかしみもあり。 |
| ○山笑ふ大笑ひとは言へねども |
安居 正浩 |
こんな句があってよい。 |
| ○犬あやす客が列車に山笑ふ |
吉田いろは |
景情整う。 |
| ○こけし彫る太き指先山笑ふ |
ひぐらし |
趣向ややおとなしいが。 |
| ○子の声の山彦が勝ち山笑ふ |
大原 芳村 |
構想力ゆたか。 |
| 山笑ふ試歩の一歩に土匂ひ |
櫻木 とみ |
「土匂ひ」利かず。 |
| てだれとて仏師童顔山笑ふ |
谷地元瑛子 |
「てだれとて」利かず。 |
| 母馬に草原歌ひ山笑ふ |
五十嵐信代 |
「草原歌ひ」利かず。 |
| 山笑ふファンは一人で笑ふもの |
大江 月子 |
「ファン」利かず。 |
| ほんのりと肩ふれ合ふて山笑ふ |
根本 文子 |
「ほんのりと」利かず。 |
| 遠ざかる汽笛移して山笑ふ |
小出 富子 |
「移して」利かず。 |
| 望遠に白馬三山山笑ふ |
つゆ草 |
「望遠に」利かず。 |
| 山笑ふ坂の頂辺膝笑ふ |
谷 美雪 |
「坂を下れば」 |
| かくばかり出会ひ名残て山笑ふ |
水野千寿子 |
心余りて言葉足らず。 |
| この景色独り占めして山笑ふ |
尾崎喜美子 |
題をもてあます。 |
| 田や畑に人働きて山笑ふ |
尾崎 弘三 |
題をもてあます。 |
| 噴煙の真つ直ぐ昇り山笑ふ |
ちちろ |
題をもてあます。 |
| 山笑ふ谷川跳ねる魚一匹 |
鷲田 裕克 |
題をもてあます。 |
| ケーブルカー車窓の外は山笑ふ |
礒部 和子 |
題をもてあます。 |
| 木々の間に漏れ落つ光山笑ふ |
中村美智子 |
題をもてあます。 |
| ひさびさの酌み交ふ友や山笑ふ |
柴田 憲 |
題をもてあます。 |
| 温暖化桜草咲き山笑ふ |
天野喜代子 |
題をもてあます。 |
| 山笑ふ頬にめしつぶ掌にむすび |
松村 實 |
題をもてあます。 |
| 山笑ふ戻りて住める田舎町 |
清水さち子 |
句意難解。 |
| 山笑ふふところに貝潜ませて |
千年 |
句意難解。 |
| 山笑ふ旅人に雪のドラえもん |
米田かずみ |
句意難解。 |
| 断崖に仏像二体山笑ふ |
金井 巧 |
趣向過ぎたり。 |
|
| 【諸葛菜】アブラナ科一年草。大根の花に似るが別物。名は諸葛孔明による。 |
| ◎急行の通過する駅諸葛菜 |
大原 芳村 |
アブラナ類の本意をよく把握。 |
| ◎蝶の舌触れる触れない諸葛菜 |
谷地元瑛子 |
新鮮なり。 |
| ◎男子なら亮と命名諸葛采 |
天野 さら |
諸葛亮の「亮」を趣向にした。 |
| ○幼子の目に力あり諸葛菜 |
堀 眞智子 |
諸葛亮が趣向か。 |
| ○剃り捨てて叩く山門諸葛菜 |
ひぐらし |
似合う景色なれども。 |
| ○禅林に青春の色諸葛菜 |
堀口 希望 |
似合う景色なれども。 |
| ○ワイシャツのよく乾く日よ諸葛菜 |
吉田いろは |
明るい光と風が見える。 |
| ○はらからの集ふ華甲の諸葛菜 |
根本 文子 |
「集ふ」で季題と融合した。 |
| ○故郷へ続く線路や諸葛菜 |
安居 正浩 |
誰の記憶にもある景色であろう。 |
| ○諸葛菜ボート乗り場に人あふれ |
小出 富子 |
場所を選ばぬ諸葛菜おもしろし。 |
| ○制服のリボンも揺れて諸葛菜 |
つゆ草 |
「リボン揺れゆく」 |
| ○転校の通学路にも諸葛菜 |
谷 美雪 |
以前の通学路がよみがえる。 |
| あけぼのに匂ひ増しくる諸葛菜 |
水野千寿子 |
特別な「匂ひ」なのか。 |
| 諸葛菜河を渡りて古城かな |
鷲田 裕克 |
三国志が趣向か。 |
| いずれとも競うことなく諸葛采 |
米田かずみ |
三国志が趣向か。 |
| 蜀の国いでて広がる諸葛菜 |
尾崎 弘三 |
三国志の説明になった。 |
| 臥牛像諸葛菜へと眼を向けて |
梅田ひろし |
臥牛像を今少し描きたし。 |
| 「諸葛菜」名札貼られる門前市 |
五十嵐信代 |
似合う景色なれども。 |
| チュニックの子の聴く音楽諸葛菜 |
西野 由美 |
諸葛菜利かず。 |
| 畦道にぽつんと揺れてる諸葛菜 |
中村美智子 |
諸葛菜に限らず。 |
| 華やぎのそちこちあふれ諸葛菜 |
清水さち子 |
諸葛菜利かず。 |
| 教へらる指さすあれが諸葛菜 |
柴田 憲 |
諸葛菜利かず。 |
| 諸葛菜紫似合ふ女流書家 |
千年 |
趣向に負けたり。 |
| 風強し薄暮の中の諸葛菜 |
尾崎喜美子 |
題をもてあます。 |
| 諸葛菜草食系でありし頃 |
金井 巧 |
題をもてあます。 |
| 雨晴れて義母の墓前に諸葛菜 |
ちちろ |
実景なるらん。 |
| 幾とせをひと昔とや諸葛菜 |
大江 月子 |
句意難解。 |
| 諸葛菜空に染まりし花の色 |
天野喜代子 |
「空に染まる」難解。 |
| 音もなき野中の鉄路諸葛采 |
松村 實 |
「音もなき」無駄。 |
| 越年の花大根に力あり |
礒部 和子 |
これは大根の花であろう。 |
|
| 海紅切絵図 |
| 川音の高きと見れば山笑ふ |
海 紅 |
| 受講者に橡の殻見せ西行忌 |
同 |
| いしぶみの四面を諸葛菜囲む |
同 |
|
|